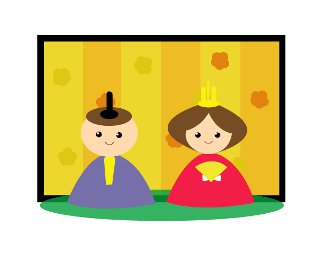身内や親戚を亡くし、喪に服している時に、娘さんやお孫さんが楽しみにしているひな祭りを行なって良いものかどうかについて考えますよね。
そこで、ひな祭りの起源なども含めて、喪中におけるひな祭りの考え方についてご紹介します。
◇ひな祭りの起源や由来とは
平安時代に中国から上巳の節句として伝わりました。
人形(ひとがた)に自分の穢(けが)れである病気や災いを移し、身代わりに背負って欲しいとの願いを込めて川などに流していました。
現在でも、神事として下鴨神社では行なわれています。
この上巳の節句とは別に、宮中では「ひいな遊び」が行なわれており、紙で作られた人形で遊んでいました。
このひいな遊びと上巳の節句の人形(ひとがた)とが結びつき、江戸時代になってから3月3日と定め、ひな祭りとして定着しました。
現在のように女の子の初節句として祝うことや、五段・七段飾りのように豪華になったのは江戸後期です。
◇ひな祭りは喪中のとき行なってはいけない?
忌中や喪中という考え方は、神道からきています。
まず忌中とは、神社本庁によりますと、故人の死を悼み、御霊(みたま)を鎮める期間で、神事や結婚式などへの出席は避け、慎んだ生活を送ります、となっています。
忌服期間は、神主さんなどの神職の方でも、一番長くて10日となっています。(以前はもっと長かったです)
では喪中ですが、こちらも神社本庁によりますと、忌明け後、悲しみを乗り越えて平常の生活に立ち返っていく期間で、神事や正月行事なども、通常通りに行ないます、となっています。
神道においては、死は最大の穢れですので、このような考え方が出てきました。
一方仏教では、このような考え方はなく、死は穢れではありませんので、忌中や喪中はありません。
神道の方であれば、ひな祭りの日が忌中や忌中直後に当たらなければ、派手なパーティーのようなものでない限り、問題ありません。
仏教徒の方であれば、そのような考え方自体がありませんので、ひな祭りを行なっても問題がありません。
◇おわりに
仏教徒の方であっても、神道の方であっても、また、無宗教の方であっても、亡くなった方のことも想いながら、お子さんやお孫さんの成長をお祝いしてはいかがでしょうか。
ただ、地域の風習や慣習などもありますので、ご家族で話し合われる方が良いかも知れません。
この情報が皆さんのお役に立てたら幸いです。